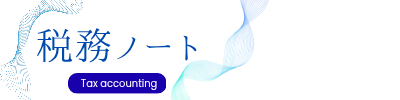【個人事業主】資料は何年保存すべき?保存期間と方法を解説!
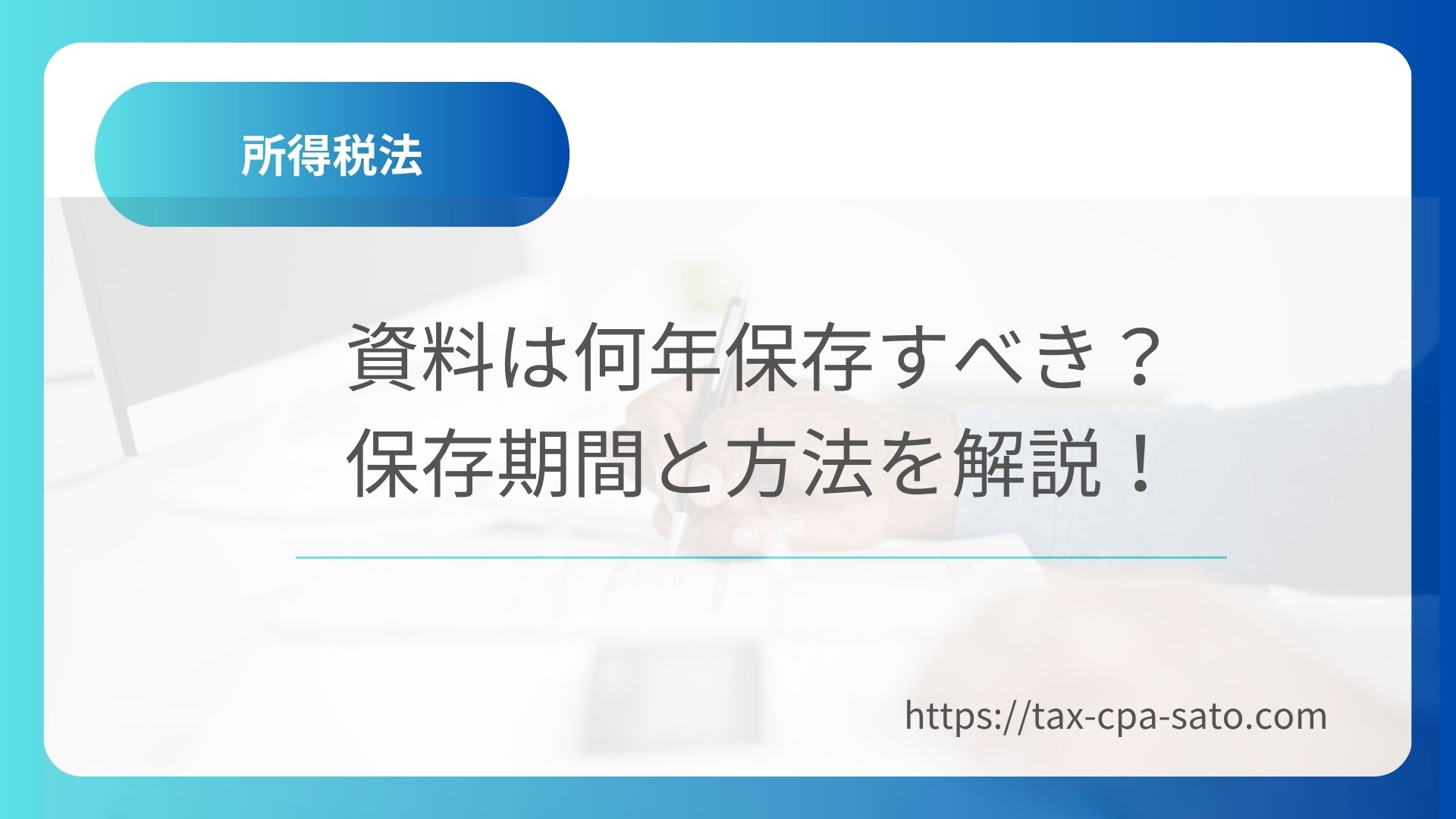
結論:個人事業主の帳簿保存年数は7年間
個人事業主は、青色申告か白色申告かに関わらず、
基本的には7年間帳簿の保存が求められます
などの法定帳簿を、原則として7年間保存する義務があります。(国税庁HP)
- 補足:小規模事業者の特例
-
小規模事業者の場合(前々年の所得が300万円以下)には一部の書類について保存期間が5年に短縮される特例もあります。
また、適格請求書(インボイス)を発行・受領する課税事業者であれば、消費税法の規定においても請求書類は7年間の保存が義務付けられています。

個人事業主(青色申告)帳簿の種類と保存期間
ここからは、青色申告を行う個人事業主が
- 「どの帳簿を」
- 「何年間」
- 「どんな形式で」
保存すればよいかを整理していきます!
青色申告をする個人事業主が保存すべき帳簿類と書類の種類、および法律で定められた保存期間は次のとおりです
- 所得税法第148および149条・同施行規則第63条
-
(青色申告者の帳簿書類)
第百四十八条 第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者は、財務省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。(青色申告書に添附すべき書類)
第百四十九条 青色申告書には、財務省令で定めるところにより、貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は純損失の金額の計算に関する明細書を添附しなければならない。(帳簿書類の整理保存)
法令検索システムより引用
第六十三条 第六十条第一項(決算)に規定する青色申告者は、次に掲げる帳簿及び書類を整理し、起算日から七年間(第三号に掲げる書類のうち、現金預金取引等関係書類に該当する書類以外のものにあつては、五年間)、これをその者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
一 第五十八条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告者の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類
三 取引に関して相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
| 帳簿・書類の種類 | 具体例 | 保存期間 | 保存方法 |
|---|---|---|---|
| 主要な帳簿(複式簿記) ※仕訳帳・総勘定元帳など | 仕訳帳/総勘定元帳/固定資産台帳 など | 7年間(原則) ※小規模事業者特例アリ | 紙または電子データ |
| 決算関係書類 | 損益計算書/貸借対照表など | 7年間 | 紙または電子データ |
| 現金・預金取引関係書類 ※現金出納に伴う証憑類 | 領収書、レシート、現金預金出納に関する伝票、預金通帳の写し など | 7年間(原則) ※小規模事業者特例アリ | 紙で受領したものは原本をファイル保管。スキャナ保存も可能 |
| その他の書類 ※取引証憑以外 | 請求書(控え含む)・納品書・見積書・契約書・注文書の写し など | 5年間 ※ただし 適格請求書等、消費税課税事業者に必要な請求書類は7年間 | 紙受領の場合は紙で保存。電子データで授受した場合は電子保存が必須 |
- ※スキャナ保存の補足
-
紙で受け取った領収書や請求書などを電子データで保存したい場合、電子帳簿保存法に沿ってスキャナやスマホ撮影で読み取り、タイムスタンプ付与または適切な保存システムで保管する方法が認められています(事前承認は不要になりました)。
ただし、解像度やカラー要件、検索機能の確保など一定の条件を満たす必要があります。
紙の原本を保存する場合はこれらの要件は気にせずそのまま7年間保管すれば問題ありません。
自社発行の請求書控えについても、紙で発行した場合は紙保存、電子発行した場合はデータ保存と、発行方法に応じて適切に保管してください。
この記事では青色申告の場合を取り扱います。(白色申告を選択するメリットは基本的にないため)

インボイス制度への対応
2023年10月から始まった適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、適格請求書発行事業者(消費税課税事業者)が発行した請求書の控えも保存義務が生じ、これは電子データで交付した場合は電子保存が必要です。
受け取った側(買い手)は従来通り請求書原本を保存しますが、仕入税額控除を受けるため適格請求書は7年間の保存が必要になる点に注意してください。
免税事業者(売上1000万円以下で消費税申告義務なし)のうちはインボイス発行義務はありませんが、取引先から受領するインボイスはしっかり保管しましょう。
電子帳簿保存法に対応した保存方法【電子帳簿保存法 保存方法】
保存方法については、紙媒体での保存だけでなく電子データでの保存も可能です。
近年の改正により、電子取引で受け取った請求書や領収書は電子データのまま保存することが法的に義務付けられました(2024年以降、本格施行)。
電子帳簿保存法に基づく対応ポイントをまとめます。
他社からメールやPDFで受領した請求書・領収書、ネット注文の受付メール、ECサイトの領収書データなどは、プリントアウトして紙で保存する方法では認められません。
これらは検索が可能な状態でシステム保管する必要があります。
通常は、クラウド会計ソフトや経費精算システムを利用しているはずですので、保管方法を気にする必要は特段無いものと思われます
紙で受け取った領収書類についてペーパーレス化したい場合は、スキャナ保存制度を活用できます。
スキャナやスマートフォンで書類を撮影し、解像度やカラー要件を満たした画像データを一定期間内にタイムスタンプ付与して保存すれば、紙の原本を破棄しても差し支えありません。
とはいえ、スキャナ保存は義務ではなく紙のまま保存しても問題ありません。無理に電子化せずとも、保管スペースや管理が煩雑でなければ紙保存でも大丈夫です。

紙の管理は大変なので個人的には電子化することをお勧めしています!
日々の帳簿(仕訳帳や総勘定元帳)を最初からパソコン上で作成している場合、そのデータも紙に出力せず電子のまま保存することが認められています。
市販の会計ソフトの多くは電子帳簿保存法に対応していますので、条件を満たしたソフトを利用すれば帳簿のPDF出力や紙印刷をしなくてもデータ保存のみで大丈夫です。
まとめ:帳簿の保存は税務調査で重要です
領収書や帳簿を長期間保存するのは手間に感じるかもしれませんが、青色申告のメリット(たとえば特別控除65万円)を受けるためには、正確で継続的な帳簿管理が欠かせません。
また、これらの帳簿や証拠書類は、税務調査の際に確認を求められる主な資料でもあります。
税務調査では、主に次のような資料が確認されます。
- 仕訳帳・総勘定元帳などの帳簿書類
- 領収書・請求書・通帳・契約書などの証拠書類
- 売上や仕入の裏付けとなる見積書・納品書・受発注データ
- 経費の支出を確認する領収証・レシート類
これらが年度ごと・取引内容ごとに整理されていれば、調査時もスムーズに対応できます。