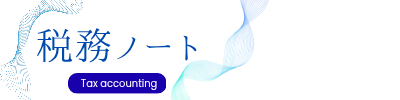配当金の益金不算入とは?短期所有株式の注意点も解説
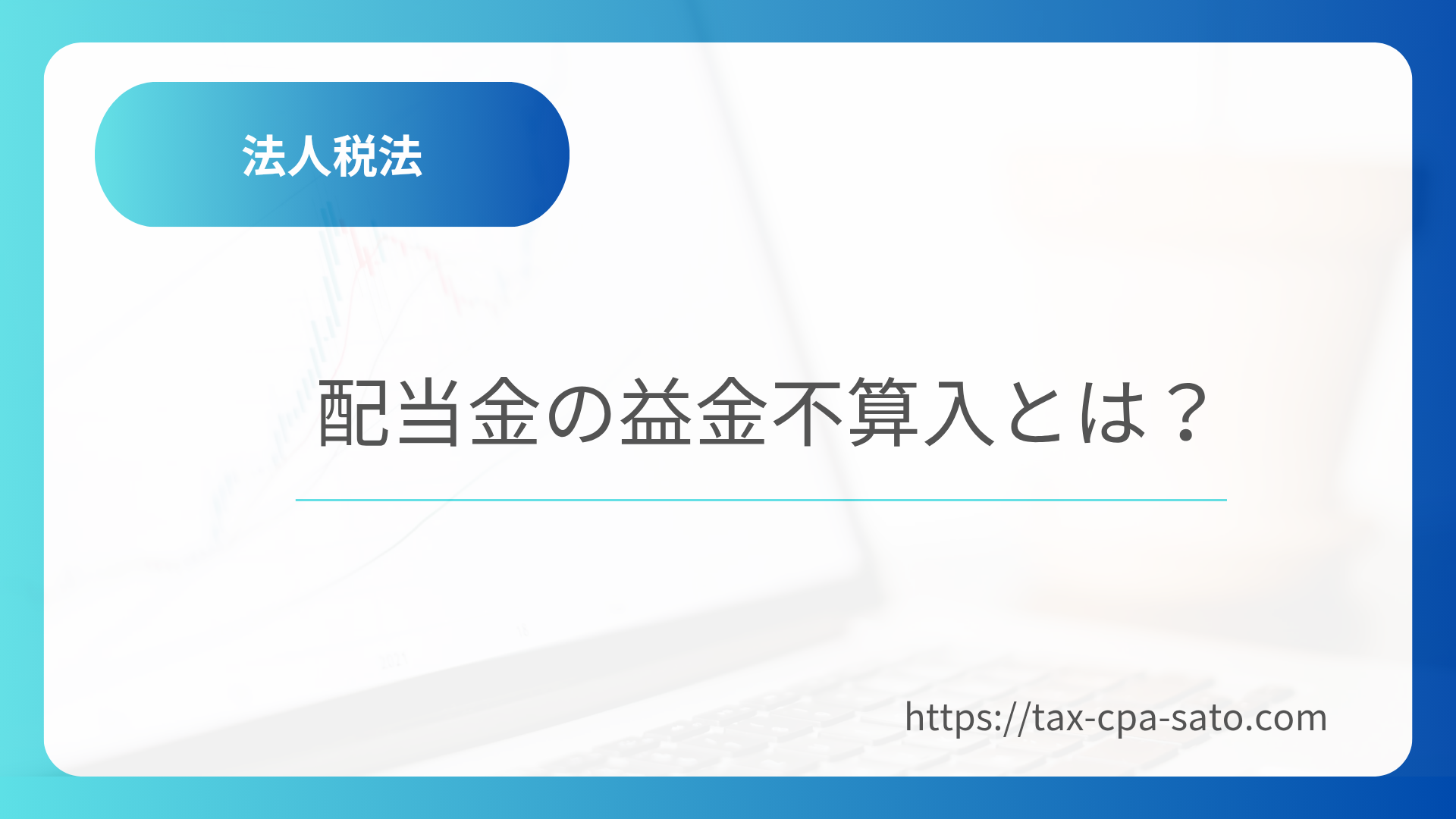
会社の経営が少しずつ軌道に乗り、余剰資金で有価証券の運用を始めると、配当金を受け取る場面も出てくるかと思います
そのときに、直面する問題が「この配当金、法人税の計算ではどう扱えばいいのだろう?」という疑問です。
実は、法人税法では受け取った配当金の一部を課税所得から除外できる「益金不算入」という仕組みがあり、条件次第で課税額が大きく変わります。
本記事では、この配当金の取り扱いと注意点を、中小法人が押さえておくべきポイントに絞って解説します。
配当金の益金不算入とは?【結論:二重課税を防ぐための制度】
法人が配当金を受け取った場合、そのまま課税すると二重課税になります。
そこで「益金不算入」という制度が設けられ、一定割合を課税所得に含めなくてよい仕組みになっています。
- 持分割合によって不算入額の割合が変動する
- 短期所有株式に該当する場合は益金算入できない
- 別表8(一)で計算した益金不算入額を別表4に転記する
持株比率で変わる益金不算入の割合
益金不算入の割合は「持株比率」で決まります。
ざっくりと次のように整理できます。
- 5%以下の出資(非支配目的株式):配当の20%が非課税
- 5%超~1/3以下の出資(その他株式):配当の50%が非課税
- 1/3超の出資(関連法人株式):配当の全額が非課税(借入金利子控除を除く)
配当金100万円を受け取った場合
- 持株比率2% → 20万円が非課税
- 持株比率10% → 50万円が非課税
- 持株比率35% → 原則100万円が非課税(控除負債利子を除く)
どの所有区分に該当するかは、少しだけ複雑なのでこちらの記事で詳細は解説しています!

短期所有株式は全額益金算入されるので要注意⚠
短期所有株式とは、
- 配当基準日の1か月以内に取得し
- 基準日後2か月以内に売却した株式を指します。
この場合、配当金は全額課税対象となり、非課税のメリットは一切使えません。
たとえば、持株比率10%で配当100万円を受けた場合、通常なら50万円が非課税です。
しかし、短期所有株式に該当すると、100万円全額が課税対象(益金算入)になります。
実務で抑えるべきポイント
配当金の益金不算入調整については、別表4で調整実施しますが、
配当金の益金不算入額の算定にあたって、別表8(一)の記入も必要になります
0801利用する会計ソフトによって仕様は異なりますが、配当金の仕訳を入力すると法人税申告に必要な別表8(1)が自動的に作成されるケースもあります
ただし、注意が必要なのは、株式の区分(持株比率や保有期間など)までは自動判定されず、マニュアルで入力しなければならない点です。
ここを誤ると、益金不算入の金額計算が正しく行われず、申告内容に影響を及ぼす可能性があります。
まとめ|
配当金の処理で大切なのは次の3点です。
- 持株比率によって益金不算入割合が決まる
- 短期所有株式に当たると全額が益金算入される
- 別表8(一)の明細で計算した結果が別表4に転記される
外国子会社配当にかかる益金不算入制度もありますが、日本国内のみで事業を行っている法人にとっては、
あまり関係のない話になりますので、この記事においては割愛します