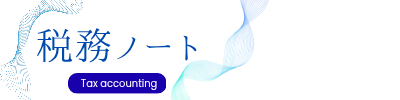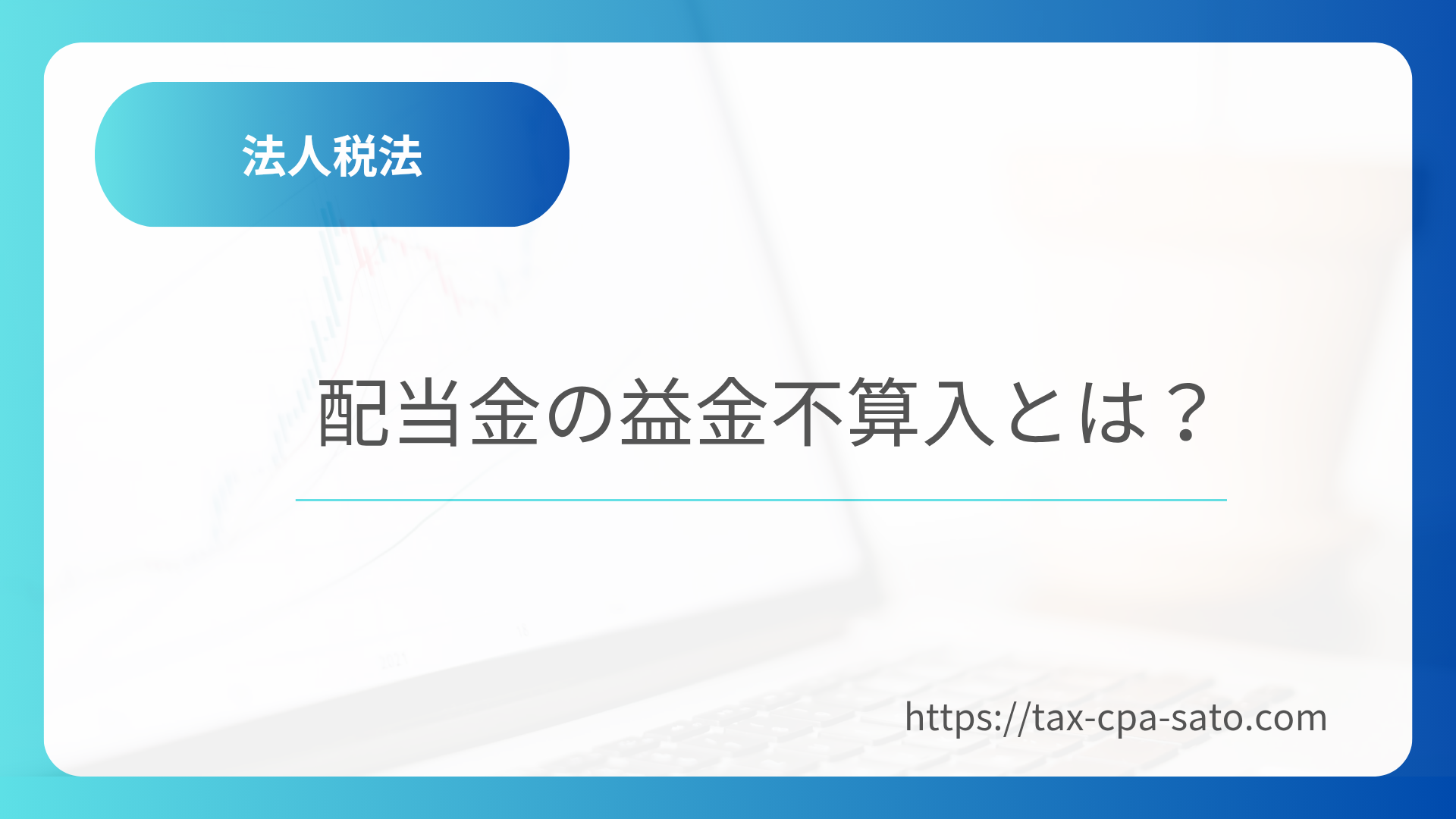【法人税】その他の株式等の益金不算入ルールを解説!
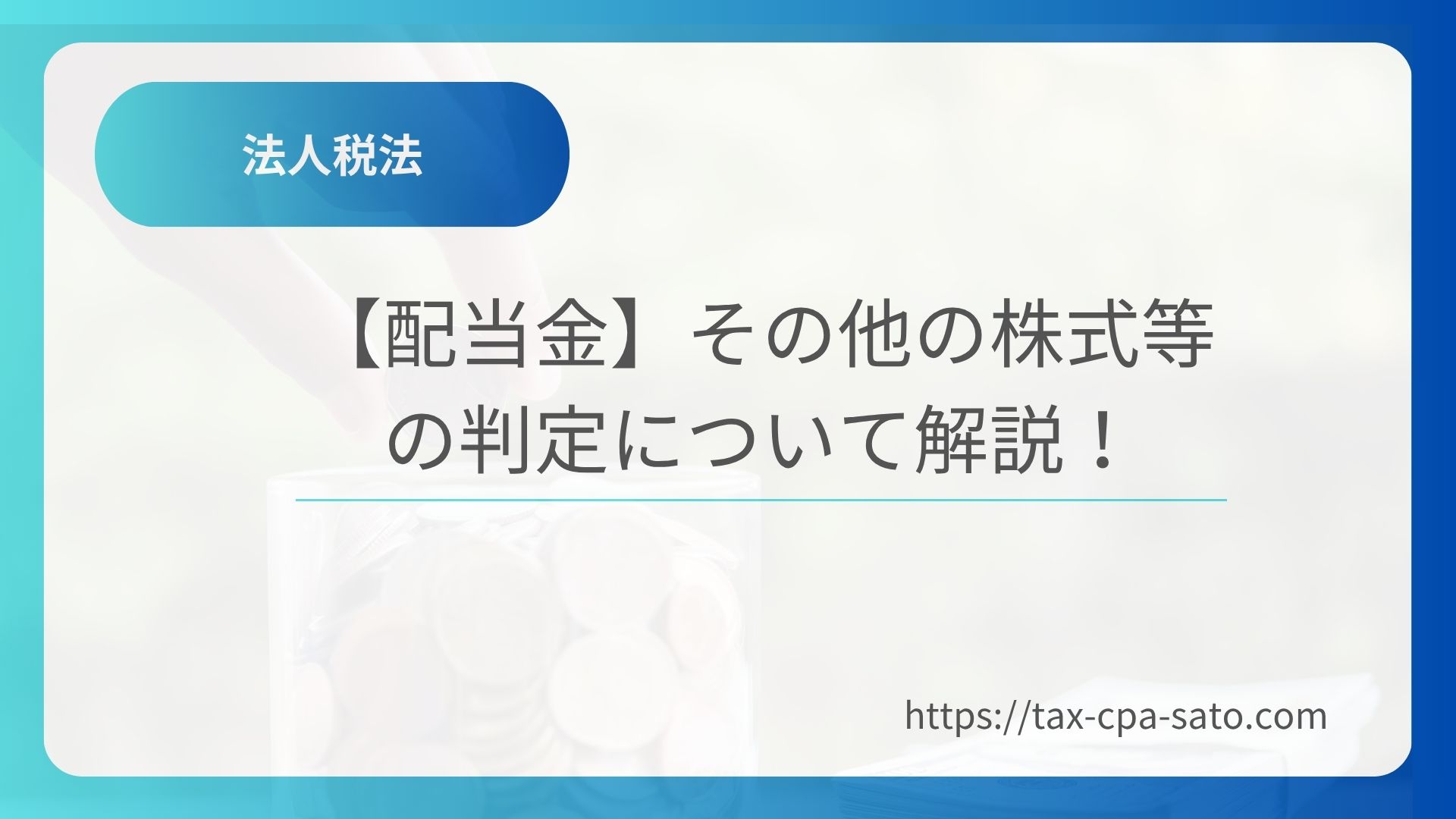
この記事では、会社が受け取る配当に関して、
- 法人税法上どのように課税が行われるのか?
- そのうちどの部分が「益金不算入」となるのか?
を解説しています。
この記事で取り扱う「その他の株式等」とは、簡単に言えば法人が他の会社の株式を5%を超えて保有し、かつ3分の1以下である場合に該当する株式をいいます。

この場合の保有とは、「保有株数」と「保有金額」のいずれかが5%を超え、かつ3分の1以下であることを意味します。
- (厳密に言えば…)
-
基本的には5%を超え1/3以下を保有している株式についてはその他の株式等になりますが、
- 完全親会社株式等
- 関連会社株式
この二つの区分に関しては、判定要件に保有期間の定めがあります。
そのため、保有期間条件を満たさないケースでは1/3以上を保有している場合であっても、「その他の株式等」に該当します。
合わせて読みたい 記事を取得できませんでした
記事を取得できませんでした
実際の条文の一部を抜粋して記載しておきます。
(受取配当等の益金不算入)
法人税法23条
第二十三条 内国法人が次に掲げる金額を受けるときは、完全子法人株式等、関連法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等に係る配当等の額にあつては当該配当等の額の百分の五十に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
この場合、受け取った配当金の50%が益金不算入の対象となります。
経営に対して支配的な影響を及ぼすわけではないため、完全子法人株式等(100%益金不算入)や関連法人株式等(3分の1超)のような取扱いは受けられませんが、
二重課税を緩和する趣旨から、一定割合(50%)が益金不算入となります。
以下に、その他の株式等に該当する代表的な事例をいくつか挙げます。
A社は取引先B社の株式を10%保有しており、期末に配当金1,000万円を受領しました。
A社はB社株を年初に8%保有しており、配当基準日(3月31日)でも同様に8%を保有していました。
その後、期末日である6月30日に株式の一部を売却し、期末時点の保有割合は2%となっています。配当金は1,200万円でした。
A社がB社の株式を2025年3月1日に40%取得し、B社の配当基準日が2025年3月31日であった場合
※なお、前回基準日は2024年9月30日であるものとする。
ポイント
これらの事例に共通して言えるのは、「その他の株式等」は経営支配の程度が低く、短期的または部分的な関係性のもとで保有される株式が該当するという点です。
「その他の株式等」は、関連法人株式等(3分の1超)と非支配目的株式等(5%以下)の中間に位置する区分であり、配当益金不算入制度の中でも判断が難しい領域です。
出資比率や保有期間の微妙な違いが税務上の調整額に大きく影響するため、事前に保有状況を整理し、区分を誤らないよう慎重な検討が求められます。